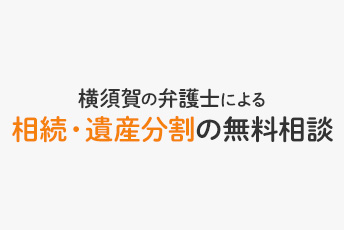アパート・駐車場など収益不動産の相続トラブル|4つの典型パターンと解決策

親が遺した財産に、賃貸アパートや月極駐車場、貸店舗などの「収益不動産」が含まれている。毎月安定した収入を生み出すこれらの資産は、ご家族にとって、本来であれば大変ありがたい遺産のはずです。しかし、その裏では、高額な資産価値や、経営方針をめぐる意見の対立から、相続人間で最も深刻な「争族」を引き起こす原因となりがちです。
この記事では、収益不動産の相続において特に発生しやすい4つの典型的なトラブルパターンと、それぞれの法的な解決策について、税理士・司法書士有資格の弁護士が分かりやすく解説します。
なぜ収益不動産の相続は、これほど揉めるのか?
収益不動産の相続が紛糾しやすい理由は、それが単なる「資産」ではなく、「事業(ビジネス)」の承継という側面を持つからです。相続人それぞれの立場や考え方の違いが、対立を深刻化させます。
- 経営に関わってきた相続人は、今後も安定収入を得るために「経営を続けたい」と考える。
- 経営に関わってこなかった相続人は、管理の手間やリスクを嫌い、「すぐに売却して現金で分けたい」と考える。
- 評価額が高額になるため、相続税の納税資金の問題も絡み、話が複雑化する。
収益不動産をめぐる4つの典型的な相続トラブル
パターン1:「売却したい」vs「経営を続けたい」という分け方の対立
最も根本的な対立です。売却して現金化する「換価分割」を望む相続人と、特定の相続人が不動産を相続して経営を続ける代わりに他の相続人にお金を支払う「代償分割」を望む相続人との間で、話し合いが平行線になります。この場合、最終的には家庭裁判所の調停や審判で解決を図ることになります。
パターン2:評価方法をめぐる対立
収益不動産の評価額は、固定資産税評価額や相続税路線価だけでなく、その物件が将来生み出す収益を基準とする「収益還元法」など、複数の算定方法があります。どの評価方法を用いるかによって金額が大きく変わるため、代償分割や換価分割の前提となる評価額そのもので、意見が激しく対立します。
パターン3:協議中の家賃収入の独り占め
相続開始後、遺産分割協議が完了するまでの間に発生した家賃収入は、法律上、遺産本体とは別に、各相続人が法定相続分に応じて取得する権利があります。しかし、物件を管理している相続人が、この家賃収入を他の相続人に分配せず、独り占めしてしまうトラブルが頻発します。
パターン4:修繕費や税金など、管理費用の負担をめぐる対立
協議中に発生した、固定資産税や、物件の修繕費、管理会社への委託費などを、誰が負担するのかで揉めるケースです。これらは原則として遺産の中から(つまり家賃収入から)支出すべきですが、その支出の妥当性を巡って対立が生じます。
最善策は、オーナー自身による「生前対策」
これらの深刻なトラブルを防ぐための最も有効な手段は、オーナーご自身が元気なうちに、計画的な生前対策を講じておくことです。
- 遺言書:経営を引き継がせたい相続人に収益不動産を相続させる旨を明確にし、他の相続人には代わりの財産を渡すなど、遺留分にも配慮した内容を作成します。
- 家族信託:後継者をあらかじめ指定し、ご自身の判断能力が低下した後も、スムーズな賃貸経営と資産承継を実現します。
当事務所は、皆様の複雑な相続問題を解決するために、他にはない強みを持っています。
- ①1972年創立、所属弁護士数約100名の実績と経験
1972年の創立以来、半世紀にわたり数多くの相続案件を手掛けてまいりました。約100名の弁護士が所属しており、それぞれの事案で蓄積された豊富な判例知識と実務経験を基に、最適な解決策をご提案します。 - ②税理士・司法書士有資格の弁護士が対応
相続問題、特に不動産や多額の財産が関わるケースでは、税務の視点が欠かせません。当事務所横須賀支店には、税理士・司法書士有資格の弁護士が在籍しています。法務と税務、登記の全方面から多角的なアドバイスをして最善の解決を目指します。 - ③グループ内で連携したワンストップサービス
当事務所は、司法書士、税理士、土地家屋調査士、不動産鑑定士、不動産仲介業者がグループ内に存在するため、各専門家と緊密に連携し、あらゆる手続きをワンストップでサポートすることが可能です。
相続にお困りの方は虎ノ門法律経済事務所にご相談ください。
収益不動産の相続は、単なる財産分けではなく、一つの「事業」を引き継ぐことに他なりません。そこには、法律、税務、不動産経営という、複数の専門領域が複雑に絡み合います。当事務所にご相談いただければ、弁護士、税理士、司法書士、そして不動産の専門家が一体となって、あなたの状況に合わせた、円満かつ合理的な解決策を導き出します。トラブルが深刻化する前に、ぜひ一度ご相談ください。
>>無料相談の流れはこちら本記事は、令和7年8月27日時点の法令等に基づき作成しております。法改正などにより、最新の情報と異なる場合がございます。具体的な事案については必ず弁護士にご相談ください。

広島大学(夜間主)で、昼に仕事をして学費と生活費を稼ぎつつ、大学在学中に司法書士試験に合格。相続事件では、弁護士・税理士・司法書士の各専門分野における知識に基づいて、多角的な視点から依頼者の最善となるような解決を目指すことを信念としています。
広島大学法科大学院卒業
平成21年 司法書士試験合格
令和3年4月 横須賀支部後見等対策委員会委員
令和5年2月 葉山町固定資産評価審査委員会委員
令和6年10月 三浦市情報公開審査会委員
令和6年10月 三浦市個人情報保護審査会委員
令和7年1月 神奈川県弁護士会横須賀支部役員幹事
令和7年3月 神奈川県弁護士会常議員