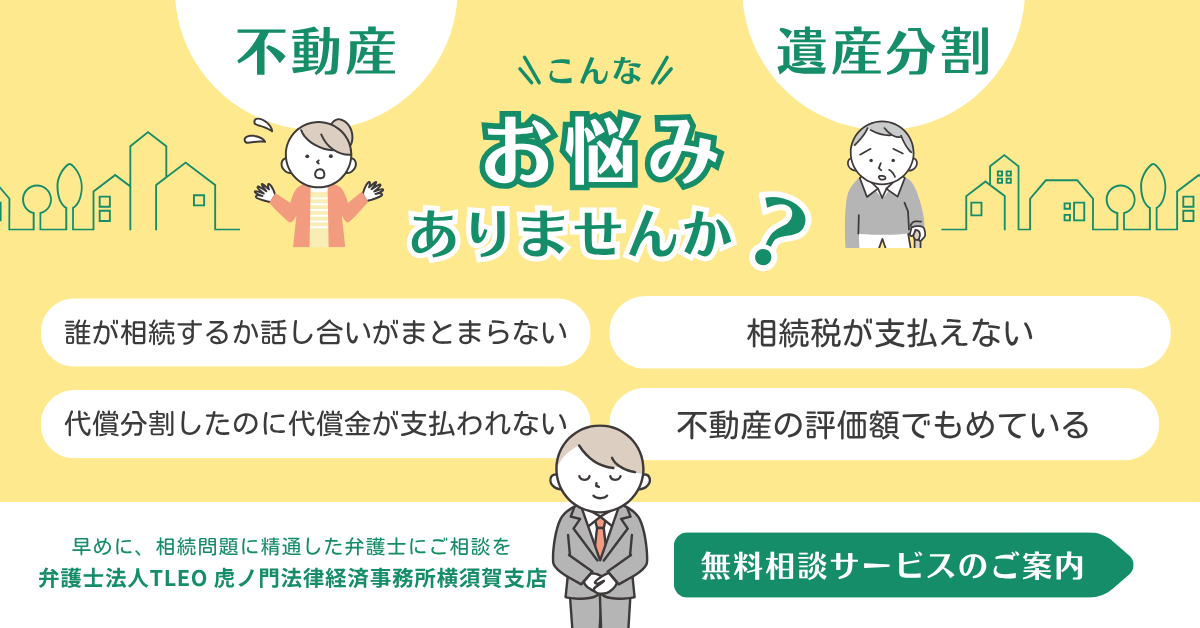不動産の評価額について折り合いがつかない
相続において不動産が含まれる場合、その評価額を巡って相続人間で意見が対立することは珍しくありません。
「この不動産はもっと価値があるはず」
「評価が高すぎる」
「なぜこの評価方法を使うのか」
といった争いが生じ、遺産分割協議が長期化してしまうケースも多く見られます。
不動産の評価額に関する争いは、単に金額の問題だけでなく、相続人それぞれの思いや将来への希望が絡み合う複雑な問題です。適切な解決を図るためには、不動産評価の基本的な仕組みを理解し、法的に適切な評価方法を選択することが重要です。本記事では、不動産評価額で揉める理由から適切な評価方法まで、税理士・司法書士有資格の相続に強い弁護士が詳しく解説いたします。
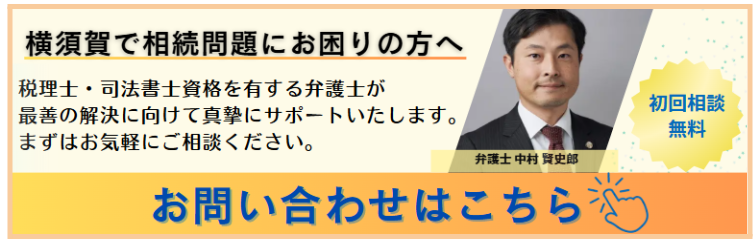
目次
なぜ?相続不動産の評価額で揉めてしまう3つの主な理由
相続不動産の評価額を巡る争いには、いくつかの典型的なパターンがあります。これらの背景を理解することで、適切な対処法を見つけることができます。
相続人間の希望や状況の違い(売却したい vs 住み続けたい)
最も多い争いの原因が、相続人それぞれの不動産に対する希望や置かれた状況の違いです。
売却を希望する相続人の視点
現金化による分割の簡素化
不動産を売却して現金化することで、相続人間での公平な分配が可能になると考える立場です。特に相続人が多数いる場合や、遠方に住んでいて管理が困難な場合に多く見られます。
維持費用の負担回避
固定資産税、管理費、修繕費等の継続的な負担を避けたいという経済的な理由から売却を希望するケースです。特に空き家となっている不動産では、この傾向が強くなります。
納税資金の確保
相続税の納税資金を確保するために、不動産の売却を必要とする場合があります。相続税は原則として現金一括納付であるため、現金化の必要性が高い状況です。
継続利用を希望する相続人の視点
居住継続の希望
被相続人と同居していた相続人や、その不動産に愛着がある相続人が居住継続を希望するケースです。家族の思い出が詰まった実家を手放したくないという感情的な理由が大きく影響します。
将来の資産価値上昇への期待
不動産市場の動向を踏まえ、将来的な価値上昇を期待して売却に反対する場合があります。特に立地条件の良い不動産では、この考え方が強くなります。
賃貸収入の確保
収益不動産の場合、継続的な賃貸収入を確保したいという経済的理由から売却に反対するケースです。
評価額への影響
このような希望の違いは、評価額に対する考え方にも大きく影響します。
売却派が実勢価格を重視する理由
売却を希望する相続人は、実際に不動産を市場で売却した場合に得られる金額、つまり実勢価格(市場価格)を重視する傾向があります。これは以下の理由によります:
実際の売却を想定しているため、市場で成立する価格が最も現実的で意味のある評価額だと考える
高い評価額により自分の相続分を多く確保したいという経済的動機
「実際に売れる金額こそが真の価値」という市場原理に基づいた考え方
不動産継続利用派が低評価額を主張する理由
一方、継続利用を希望する相続人は、固定資産税評価額や相続税評価額等の低い評価額を主張することが多くなります:
代償分割を行う場合、低い評価額により他の相続人への代償金を抑えたいという経済的動機
「売却しないのだから売却価格は関係ない」という論理
税務上の評価額(固定資産税評価額等)の方が公的で客観的だという主張
具体的な価格差の例
実際には、これらの評価額には大きな開きがあります
|
【評価額例】 実勢価格:3,000万円 相続税評価額(路線価):約2,400万円(公示価格の80%が目安とされ、一般に実勢価格より低い価格となります) 固定資産税評価額:約2,100万円(公示価格の70%が目安とされ、相続税評価額よりさらに低い価格となる傾向があります) このような場合、売却派と継続利用派の間で約900万円もの評価額の差が生じることになり、代償分割での代償金額に大きな影響を与えます。 |
採用する評価方法や基準に対する認識のズレ
不動産には複数の評価方法があり、どの方法を採用するかによって評価額が大きく異なります。この点に関する認識のズレも争いの大きな原因となります。
評価方法に関する知識不足
一物四価の理解不足
不動産には公示価格、固定資産税評価額、相続税評価額、実勢価格という4つの価格があることを理解していない相続人が多く、この知識不足が混乱を招きます。
税務上の評価と遺産分割での評価の混同
相続税申告で使用する相続税評価額と、遺産分割協議で使用すべき時価(実勢価格)を混同するケースが頻繁に見られます。
【重要】遺産分割協議では「時価」を基準にするのが原則
遺産分割協議において不動産を評価する場合、法律上は実際に売れた額である時価(実勢価格)を基準とすることが原則とされています。なお、評価額を算定する基準となる時点は、相続が開始した時点ではなく、実際に遺産分割を行う時点(遺産分割協議が成立した時点)とするのが原則です。不動産価格が変動している場合は、この基準時の違いが評価額に大きく影響します。
不動産の遺産分割を弁護士に依頼するメリット
相続問題では不動産が絡むケースが少なくありません。不動産がある場合は「どのように分けるか」という分け方を決めるのが難しく、また登記を含め手続きがとても複雑です。あわせて、マンションや土地のように価値があるものばかりではなく、田舎の田んぼや畑は所有するとむしろマイナスになってしまう場合もあり、もめてしまうケースが多いです。弁護士にご相談いただければ、不要な争いを避けつつ迅速に分割方法を確定させられます。
当事務所の横須賀支店は司法書士資格を有する弁護士が法律相談に対応します。不動産の知識や不動産登記について精通しているため、複雑な手続きを円滑に行うことができます。安心してお任せください。
相続にお困りの方は虎ノ門法律経済事務所にご相談ください
虎ノ門法律経済事務所は、不動産評価額を巡る争いをはじめとする相続トラブルの解決において、豊富な実績と経験を有する法律事務所です。複雑な不動産評価の問題についても、多数の解決事例があります。
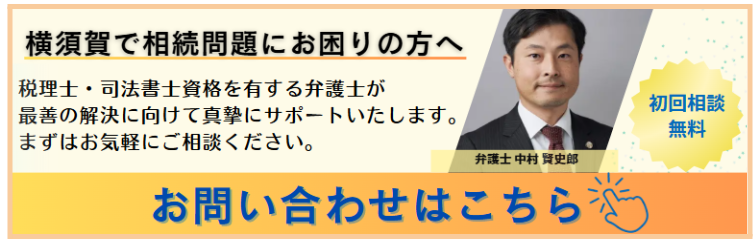
弁護士法人TLEO 虎ノ門
法律経済事務所横須賀支店の


-
1972年創立
所属弁護士数約100名の実績と経験虎ノ門法律経済事務所では、1972年の創立以来、数多くの事件を取り扱ってまいりました。現在では元家庭裁判所裁判官等グループ全体で約100名の弁護士が所属しております。

-
グループ内で連携したワンストップ
サービス虎ノ門法律経済事務所では、所属しております税理士・司法書士・行政書士・社会保険労務士・土地家屋調査士・不動産鑑定士といった士業の方と連携したサービスをご提供しております。

-
司法書士と税理士資格を有する
弁護士が対応相続問題は税務・登記・法務が絡み合います。当事務所は、弁護士に加え税理士・司法書士資格も有する弁護士が、多角的な視点からお客様に最適な解決策をご提案。安心してご相談ください。

-
相続の年間相談実績約1000件
※事務所全体年間相談実績1000件以上を誇る当事務所が、豊富な経験と蓄積された専門知識・ノウハウで皆様の相続をサポートいたします。


広島大学(夜間主)で、昼に仕事をして学費と生活費を稼ぎつつ、大学在学中に司法書士試験に合格。相続事件では、弁護士・税理士・司法書士の各専門分野における知識に基づいて、多角的な視点から依頼者の最善となるような解決を目指すことを信念としています。
広島大学法科大学院卒業
平成21年 司法書士試験合格
令和3年4月 横須賀支部後見等対策委員会委員
令和5年2月 葉山町固定資産評価審査委員会委員
令和6年10月 三浦市情報公開審査会委員
令和6年10月 三浦市個人情報保護審査会委員
令和7年1月 神奈川県弁護士会横須賀支部役員幹事
令和7年3月 神奈川県弁護士会常議員