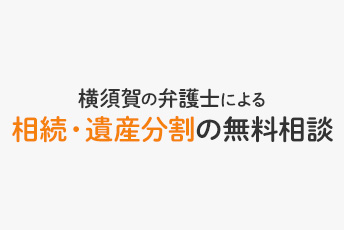遺産分割に関連する訴訟の種類
遺産分割に関連する訴訟は、遺産を不当に使い込んでいる相続人が存在した場合の不当利得返還請求訴訟が代表的といえます。
しかし、それ以外にも、そもそも遺産分割を行うにあたっての事実関係の認定の段階で主張が対立している場合には、民事訴訟を申し立てる「事実関係を争う訴訟」というものがあります。
主に以下のよう類型があります。
- ・相続人の範囲について争うもの
- ・遺産(相続財産)の範囲について争うもの
- ・遺言の有効性・無効性を争うもの(いわゆる遺言無効訴訟)
それぞれ見ていきましょう。
目次
相続人の範囲について争う訴訟
一つ目の類型として相続人であることを争う訴訟があります。相手方に、相続人として故人の財産を受け取る権利が存在するかについて争われるものです。
相続人の地位を有していないことの確認訴訟を起こすケースとして、他の相続人に相続欠格事由(民法891条)が存在しているような事例が考えられます。
※相続の欠格事由とは
故意に被相続人や先順位の相続人を死亡させたり、遺言を破棄したりした場合等に、相続人となることができなくなることです。(具体的な相続欠格事由は民法891条に規定されています)。
また、戸籍上は相続人であるが血縁がないケースなどでも、相続人の地位を有していないことの確認訴訟が提起されることがあります。
遺産(相続財産)の範囲について争う訴訟
相続人の範囲について争う訴訟は、「遺産確認訴訟」と呼ばれます。
「遺産確認訴訟」とは、相続財産になりえるべき遺産(相続財産)が、遺産の範囲に含まれているか、について争われる訴訟です。
遺産確認訴訟の例として、名義預金に対するものがあります。名義預金とは実質的には被相続人の預金であるのに、名義が相続人になっている預金等を指します。
親が子供に内緒で子供名義の口座を作成してその口座にお金を貯金し続けているケースなどが名義預金としてよく問題となります。
遺言の有効性・無効性を争う訴訟(いわゆる遺言無効訴訟)
遺言無効訴訟とは、名前の通り、故人が生前に遺していた遺言に対して、その遺言が無効であると主張して起こす訴訟のことです。
遺言無効訴訟を起こすケースとしては、遺言者が遺言作成時に既に認知症であったため遺言の無効を主張するケースなどが良くあります。
具体的には、母が亡くなり、遺言が見つかって、その通りに相続をしようとしたところ、明らかに弟に不利な内容の記載があったため、遺言の作成日を確認したところ、母が認知症になった後の時期に作成されていたことが発覚し、遺言は無効であると主張して訴訟を提起するケースが考えられます。
当事務所では、相続・遺産分割に関連する訴訟についてのサポートをさせていただきます。
話し合いや調停の段階で、上記のような事実関係に争いがある場合に、話し合っても平行線を辿る可能性が高いとお考えの場合には、訴訟も視野に入れるべきです。
調停中に上記のような遺産分割の前提となる問題が発生した場合は、調停を中断したり、終了したりすることになるため、訴訟が解決に適切なケースでは、早めに弁護士に相談すべきといえるでしょう。
ただ、訴訟を提起するかどうかの判断は、相続の全体像の中で、訴訟の結果などを想定して行うべきです。
遺産分割審判や関連する訴訟の流れ、訴訟になった場合の可能性などについては、事前に弁護士にご相談いただき、方針を決定するとよいでしょう。
当事務所では、弁護士の資格の他、税理士・司法書士有資格であり、数々の相続事件を解決している相続に強い弁護士の豊富な経験から、遺産分割に関連する訴訟についての結果を想定してベストな方針のご提案をさせていただきます。
一方で、訴訟を起こすことになりますので、お客様単独で進めることは困難であると考えられます。心労も多くなりやすいです。私たち弁護士もそのようなお客様の様子を見ていていたたまれなくなることもしばしばあります。
そこで、当事務所では遺産分割に関連する訴訟についてのサポートをご提案させていただいております。
初回のご相談は45分無料です
当事務所では、お電話でご予約いただき、事務所にお越しいただきまして、相談を受けております。
遺産分割に関連する訴訟のご相談は、初回45分無料でお受けしております。
相続のご相談は繊細な内容が多く含まれていますので、弁護士の守秘義務に基づいてお伺いした内容については徹底管理をさせていただきます。
ご安心してご相談いただける体制を作る努力をしております。
遺産分割に関連する訴訟について弁護士から提案させていただきます。
遺産分割に関連する訴訟(相続人の地位不存在確認訴訟や遺言無効訴訟など)のご依頼をお受けする前には、丁寧なヒアリングをさせていただき、訴訟の結果を想定し、訴訟の必要があるかどうかについて、全体の方針をお伝えさせていただきます。また、仮にご依頼いただく場合にも、どのような形で進めるかを提案させていただき、ご相談者様の不安を解消できるよう努めさせていただいております。

広島大学(夜間主)で、昼に仕事をして学費と生活費を稼ぎつつ、大学在学中に司法書士試験に合格。相続事件では、弁護士・税理士・司法書士の各専門分野における知識に基づいて、多角的な視点から依頼者の最善となるような解決を目指すことを信念としている。
広島大学法科大学院卒業
平成21年 司法書士試験合格
令和3年4月 横須賀支部後見等対策委員会委員
令和5年2月 葉山町固定資産評価審査委員会委員
令和6年10月 三浦市情報公開審査会委員
令和6年10月 三浦市個人情報保護審査会委員
令和7年1月 神奈川県弁護士会横須賀支部役員幹事
令和7年3月 神奈川県弁護士会常議員