特別縁故者とは何ですか?
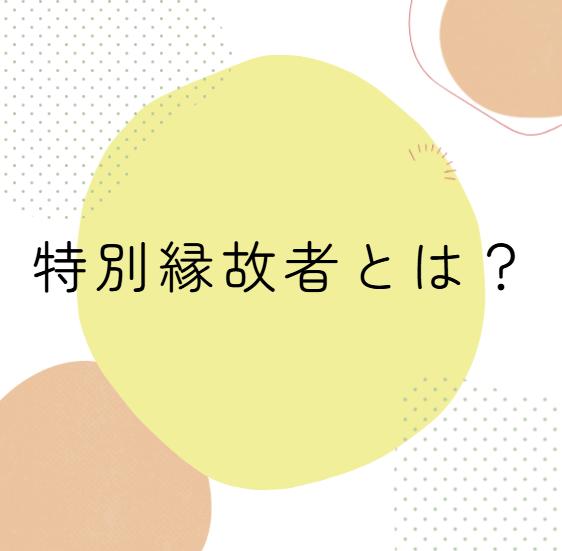
特別縁故者(とくべつえんこしゃ)とは、被相続人(亡くなった方)の相続人がいない場合において、被相続人と特別な関係があった人物のことを指します。通常、相続人がいない場合、被相続人の財産は国庫に帰属しますが、特別縁故者として家庭裁判所の審判で認められた場合、相続人ではなくとも被相続人の財産の全部または一部を取得することができます。この制度は、被相続人の生前の人間関係や支援関係を尊重し、財産がより適切に承継されるように設けられたものです。
>>希望の遺言書を作成したい方はこちら
1. 特別縁故者の要件
特別縁故者として認められるには、以下のような条件を満たす必要があります:
(1) 相続人がいないこと
被相続人に配偶者や子、親、兄弟姉妹などの法定相続人が存在しない場合、特別縁故者の制度が適用されます。相続人がいる場合はこの制度は利用できません。
(2) 特別な縁故関係があること
特別縁故者として認められるには、被相続人と特別な関係があったと認められる必要があります。
具体的には以下の例が挙げられます:
生計を同じくしていた者:
同居して生活を共にしていたパートナーや内縁関係にある人など。
被相続人の療養看護をしていた者:
生前に被相続人の介護や世話をしていた人。
その他特別の縁故がある者:
親族でなくとも、被相続人に対して経済的支援や精神的支援を行っていた友人や知人など。
家庭裁判所は、個別の事情を総合的に考慮して「特別の縁故」があるかどうかを判断します。
2. 特別縁故者として財産を取得する手続き
特別縁故者が被相続人の財産を取得するには、以下の手続きを行う必要があります:
(1) 相続財産清算人の選任
被相続人に相続人がいない場合、家庭裁判所に申立てをして相続財産清算人を選任する必要があります。この相続財産清算人が、被相続人の財産を管理・清算し、債務の弁済などを行います。
>>遺産の内容を調査して欲しい方はこちら
(2) 特別縁故者としての申立て
相続財産清算人による相続人の捜索や債権者への通知などの手続きが終了した後、特別縁故者は家庭裁判所に対し特別縁故者に対する財産分与の申立てを行います。この申立ては、官報に掲載された相続権主張の催告期間満了後、3か月以内に行わなければなりません。
(3) 家庭裁判所の審判
家庭裁判所が、申立人が特別縁故者に該当するかを審査します。縁故の内容や財産取得の妥当性が審理された上で、財産分与額が決定されます。
3. 特別縁故者に認められない場合
家庭裁判所が特別縁故者に該当しないと判断した場合、被相続人の財産は国庫に帰属します。
4. 結論
特別縁故者とは、相続人がいない場合に、被相続人と特別な関係があった人が家庭裁判所の審判に基づき財産を取得できる制度です。申立てには手続きや証拠が必要であり、場合によっては専門的な判断を求められることもあります。申立てを検討している場合は、弁護士などの専門家に相談し、適切な対応を進めることをお勧めします。

広島大学(夜間主)で、昼に仕事をして学費と生活費を稼ぎつつ、大学在学中に司法書士試験に合格。相続事件では、弁護士・税理士・司法書士の各専門分野における知識に基づいて、多角的な視点から依頼者の最善となるような解決を目指すことを信念としています。
広島大学法科大学院卒業
平成21年 司法書士試験合格
令和3年4月 横須賀支部後見等対策委員会委員
令和5年2月 葉山町固定資産評価審査委員会委員
令和6年10月 三浦市情報公開審査会委員
令和6年10月 三浦市個人情報保護審査会委員
令和7年1月 神奈川県弁護士会横須賀支部役員幹事
令和7年3月 神奈川県弁護士会常議員















