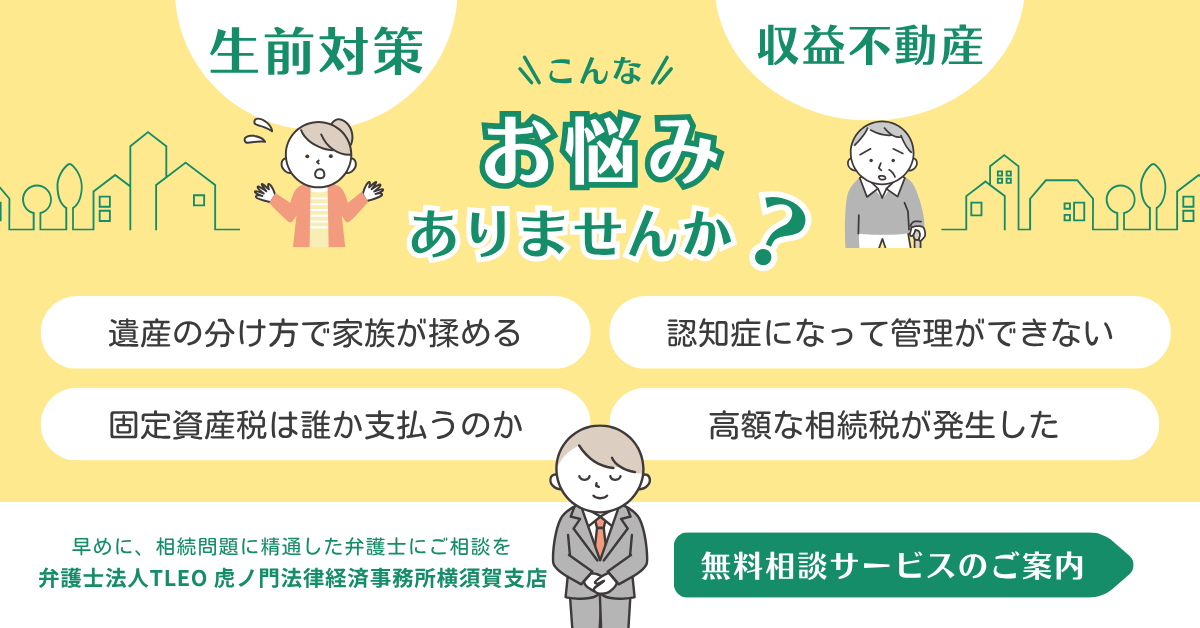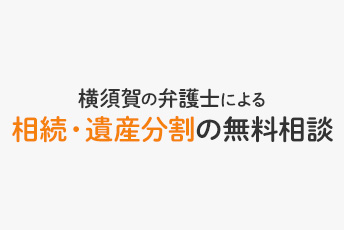賃貸経営者・不動産オーナーのための相続対策サポート
賃貸アパートやマンション、駐車場、貸店舗などの収益不動産は、ご家族にとって安定した収入を生み出す、かけがえのない優良資産です。しかし、いざ相続となると、その評価額の大きさから、高額な相続税や、相続人間での深刻な遺産分割トラブルの原因となりがちです。また、ご自身の認知症による資産凍結のリスクも考えなければなりません。
賃貸経営の成功は、適切な管理と計画的な経営戦略にかかっています。それは、次世代への「相続」という最終局面においても、何ら変わりありません。あなたの築き上げた大切な資産を、円満かつ円滑に、次の世代へと引き継ぐために、専門家と共に計画的な相続対策を始めませんか。
こんなお悩みはありませんか?不動産オーナー特有の相続問題
- 複数の収益不動産を、子供たちの間でどう公平に分ければ良いか分からない。
- 相続税がどのくらいかかるのか、納税資金をどう準備すれば良いか見当もつかない。
- 子供たちが不動産を共有名義にすることで、将来「負動産」化しないか心配だ。
- 経営に関わってきた長男に事業を継がせたいが、他の子供たちとの間で不公平にならないか。
- 自分が認知症になった場合、物件の管理や売却ができなくなる「資産凍結」が怖い。
- 相続対策として有効な「家族信託」や「法人化」に興味があるが、仕組みが複雑で分からない。
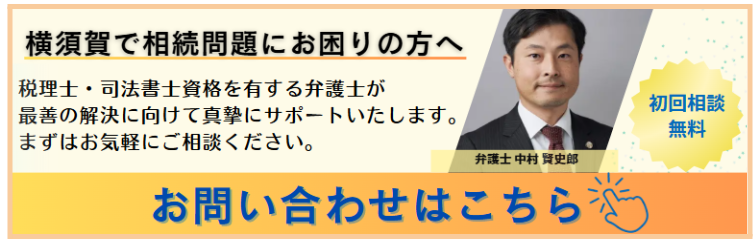
当事務所が提案する、不動産オーナーのための4つの生前対策
私たちは、法律と税務の専門家として、あなたの資産状況とご家族への想いを深く理解し、円満な資産承継を実現するための最適なプランを、オーダーメイドで設計・実行します。
①「遺言書」による分割方法の指定と、争族の防止
最も基本的かつ強力な対策が、法的に有効な遺言書の作成です。「長男には収益アパートAを、次男には自宅と預貯金を」というように、財産の分け方を具体的に指定することで、相続人同士が無用な話し合いで揉める「争族」を未然に防ぎます。
②「生前贈与」による計画的な資産移転と相続税対策
暦年贈与や相続時精算課税制度などを活用し、計画的に生前から子供たちへ資産を移転することで、将来の相続財産そのものを圧縮し、相続税の負担を軽減するプランをご提案します。
③「家族信託」による認知症対策と円滑な資産承継
不動産オーナーにとって、今最も注目されている対策が「家族信託」です。信頼できるご家族(例えば長男)に財産の管理・処分権限を託すことで、万が一ご自身が認知症になっても、資産が凍結されることなく、賃貸経営の継続や、計画的な不動産の売却・買換えが可能になります。また、二次相続以降の資産の承継先まで指定できるなど、遺言よりも柔軟な資産承継を実現できます。
④「法人化」による所得税・相続税対策
複数の物件を所有し、事業規模が大きくなっている場合には、資産管理会社を設立して不動産を法人所有に切り替える「法人化」が有効な場合があります。個人にかかる高い所得税率を、法人税率に転換できるほか、役員報酬の活用などで、相続税対策にも繋がります。
当事務所は、皆様の複雑な相続問題を解決するために、他にはない強みを持っています。
- ①1972年創立、所属弁護士数約100名の実績と経験
1972年の創立以来、半世紀にわたり数多くの相続案件を手掛けてまいりました。約100名の弁護士が所属しており、それぞれの事案で蓄積された豊富な判例知識と実務経験を基に、最適な解決策をご提案します。 - ②税理士・司法書士有資格の弁護士が対応
相続問題、特に不動産や多額の財産が関わるケースでは、税務の視点が欠かせません。当事務所横須賀支店には、税理士・司法書士有資格の弁護士が在籍しています。法務と税務、登記の全方面から多角的なアドバイスをして最善の解決を目指します。 - ③グループ内で連携したワンストップサービス
当事務所は、司法書士、税理士、土地家屋調査士、不動産鑑定士、不動産仲介業者がグループ内に存在するため、各専門家と緊密に連携し、あらゆる手続きをワンストップでサポートすることが可能です。
相続にお困りの方は虎ノ門法律経済事務所にご相談ください。
不動産オーナーの相続対策は、ご家族の想い、法律、そして税金という、三つの要素を完璧に調和させる、高度な専門知識が要求されるオーケストラの指揮のようなものです。一つのミスが、将来に大きな不協和音(トラブル)を生じさせかねません。あなたの築いた大切な資産と、ご家族の未来を守るために、ぜひ一度、私たち専門家にご相談ください。あなたに寄り添い、最善のハーモニーを奏でるための指揮を、責任をもって執らせていただきます。
>>無料相談の流れはこちら本記事は、令和7年8月14日時点の法令等に基づき作成しております。法改正などにより、最新の情報と異なる場合がございます。具体的な事案については必ず弁護士にご相談ください。

広島大学(夜間主)で、昼に仕事をして学費と生活費を稼ぎつつ、大学在学中に司法書士試験に合格。相続事件では、弁護士・税理士・司法書士の各専門分野における知識に基づいて、多角的な視点から依頼者の最善となるような解決を目指すことを信念としています。
広島大学法科大学院卒業
平成21年 司法書士試験合格
令和3年4月 横須賀支部後見等対策委員会委員
令和5年2月 葉山町固定資産評価審査委員会委員
令和6年10月 三浦市情報公開審査会委員
令和6年10月 三浦市個人情報保護審査会委員
令和7年1月 神奈川県弁護士会横須賀支部役員幹事
令和7年3月 神奈川県弁護士会常議員