遺言書と違う内容で遺産分割は可能?贈与税は?
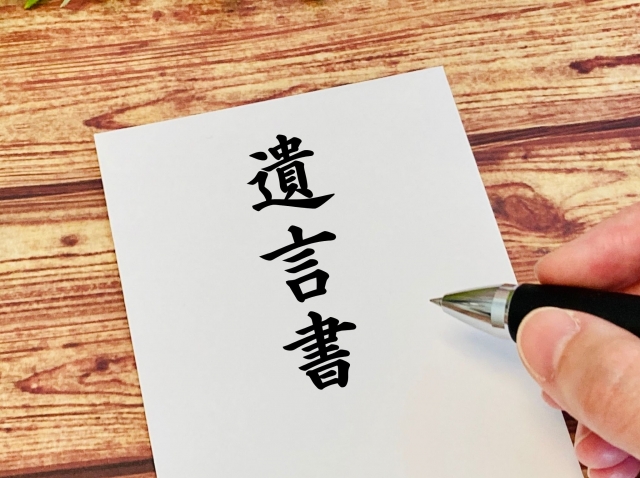
「故人の遺言書が見つかったけれど、書かれてから時間が経っており、今の家族の実情とは合わない…」 「相続人みんなで話し合った結果、遺言書とは違う分け方で合意できそうだが、法的に問題はないのだろうか?」 「遺言書と違う分け方をした場合、贈与税がかかる?」
このようなトラブルについて当事務所も横須賀・逗子・葉山・三浦エリアの方からよくご相談を受けます。
遺言書は、故人の最終的な意思を示す非常に重要なものですが、時として、残されたご家族の状況にそぐわないケースも存在します。
この記事では、遺言書の内容とは異なる遺産分割は可能なのか、そしてその場合の税金はどう扱われるのかという、多くの方が抱える疑問について、国税庁の見解も踏まえながら税理士・司法書士有資格の弁護士が徹底的に解説します。
結論:遺言書と異なる内容の遺産分割は「可能」です
まず結論から申し上げますと、相続人全員の合意があれば、遺言書の内容と異なる遺産分割協議を行うことは法的に可能です。
遺言書は絶対的なものではなく、相続人全員が納得しているのであれば、その合意が尊重されるのが原則です。しかし、この「可能」という結論には、いくつかの重要な要件と、特に税務上の問題点が存在します。安易に判断せず、正しい知識を身につけることが極めて重要です。
遺言書と異なる遺産分割が認められるための3つの要件
以下の要件を満たしていないと、遺言書と異なる分割は認められません。
要件1:相続人全員が合意していること
最も基本的な要件です。相続人のうち一人でも遺言書通りの分割を主張した場合、遺産分割協議は成立せず、原則として遺言書の内容が優先されます。全員が納得して合意形成することが大前提となります。
要件2:遺言で「遺贈」がされていないこと(または受遺者の同意があること)
遺言書で、法定相続人以外の人や団体(例:お世話になった友人、NPO法人など)へ財産を渡す「遺贈(いぞう)」が指定されている場合、その財産を受け取る人(受遺者)の同意がなければ、勝手に内容を変更することはできません。受遺者がいる場合は、その方の合意も必要となります。
要件3:遺言執行者がいる場合、その同意を得ていること
遺言執行者とは、遺言の内容を実現するために指定された人のことです。遺言執行者は遺言内容を実現する義務を負っているため、もし遺言書と異なる分割を行いたいのであれば、遺言執行者の同意を得る必要があります。執行者が反対した場合は、原則として遺言書に従うことになります。
【重要】相続税・贈与税の扱いはどうなる?
遺言書と異なる遺産分割を行う際に、多くの方が「遺言で財産をもらうはずだった人から、別の相続人へ贈与したと見なされ、贈与税がかかるのではないか?」と心配されます。
ご安心ください。国税庁の見解によれば、法定相続人間での遺産分割であれば原則として贈与税はかかりません。
税金の計算は、以下のルールで行われます。
【税金のルール】
相続人の全員の合意によって遺言書と異なる遺産分割を行った場合、その『実際に分割した内容』に基づいて相続税の計算を行います。
つまり、「遺言書に書かれた内容」ではなく、あくまで「最終的に合意した分割内容」で各人の相続税が計算されるため、相続人間での贈与の問題は生じないのです。
ただし、これは法定相続人間の正式な合意があることが大前提です。また、この取扱いは法定相続人間のやり取りに限った話であり、当初の遺言やその後の協議によって法定相続人以外の方が財産を取得する場合には、別途、贈与税などが課税される可能性があります。
また、一部の人だけで勝手に財産を動かすと、贈与と見なされるリスクがありますのでご注意ください。
参考:国税庁 タックスアンサー No.4176 遺言書の内容と異なる遺産分割
遺言書と異なる分割を行う際のその他の注意点
税金以外にも、いくつか注意すべき点があります。
遺留分との関係
合意した分割内容が、結果的に誰かの遺留分(法律で保障された最低限の遺産の取り分)を侵害するような内容になっていないか注意が必要です。一度は合意しても、後から「やはり遺留分は主張したい」というトラブルに発展する可能性もゼロではありません。原則的に遺産分割終了後は遺留分の主張はできませんが、遺恨を残すことになりかねませんので、その点については配慮するのが望ましいでしょう。
>> 遺産をもらえない内容の遺言書が見つかった(遺留分について)
合意内容の書面化
口約束だけでは「言った、言わない」のトラブルの元です。全員で合意した内容は、必ず法的に有効な「遺産分割協議書」として作成し、全員が署名・押印して保管することが不可欠です。
なぜ専門家への相談が不可欠なのか?
ここまで見てきたように、遺言書と異なる遺産分割は、法務と税務の両面で複雑な問題が絡み合います。ご自身たちだけで判断を進めるのは非常にリスクが高く、専門家である弁護士への相談が不可欠と言えます。
私たち虎ノ門法律経済事務所は、皆様の相続を円満かつ有利に進めるための盤石な体制を整えています。
理由①:税務リスクを正確に分析・回避できる【ワンストップ対応】
遺言書と異なる分割を検討する上で、相続税・贈与税のリスク分析は最優先事項です。当事務所には弁護士資格と税理士資格を併せ持つ専門家が在籍しているため、法的な有効性の判断と税務リスクの分析を同時に、かつ高い精度で行うことが可能です。
さらに、グループ内の税理士法人と緊密に連携し、法務から税務申告まで一貫したワンストップサービスをご提供。お客様が複数の事務所を訪ねる手間や、専門家間の連携不足によるリスクを解消します。
理由②:将来の紛争を防ぐ遺産分割協議書を作成できる【豊富な実績】
当事務所は1972年創立、所属弁護士数約100名という長年の歴史と経験を有します。その豊富な実績に基づき、不動産の評価や株式の承継など、複雑な財産が含まれる場合でも、あらゆるトラブルを想定した、将来にわたって安心できる遺産分割協議書の作成をサポートいたします。
相続にお困りの方は虎ノ門法律経済事務所にご相談ください
遺言書は故人の大切な想いです。その想いを尊重しつつ、残されたご家族が円満に、そして納得して新たな一歩を踏み出すためのお手伝いをすることが、私たちの使命です。
遺言書の内容でお悩みの方、相続手続きに不安がある方は、ぜひ一度、私たちにご相談ください。虎ノ門法律経済事務所では、相続に関する初回のご相談は無料でお受けしております。まずはお気軽にお問い合わせいただき、皆様のお悩みをお聞かせいただければ幸いです。
本記事は、令和7年8月27日時点の法令等に基づき作成しております。法改正などにより、最新の情報と異なる場合がございます。具体的な事案については必ず弁護士にご相談ください。

広島大学(夜間主)で、昼に仕事をして学費と生活費を稼ぎつつ、大学在学中に司法書士試験に合格。相続事件では、弁護士・税理士・司法書士の各専門分野における知識に基づいて、多角的な視点から依頼者の最善となるような解決を目指すことを信念としています。
広島大学法科大学院卒業
平成21年 司法書士試験合格
令和3年4月 横須賀支部後見等対策委員会委員
令和5年2月 葉山町固定資産評価審査委員会委員
令和6年10月 三浦市情報公開審査会委員
令和6年10月 三浦市個人情報保護審査会委員
令和7年1月 神奈川県弁護士会横須賀支部役員幹事
令和7年3月 神奈川県弁護士会常議員















