相続人に認知症の方がいる場合はどうなるの?
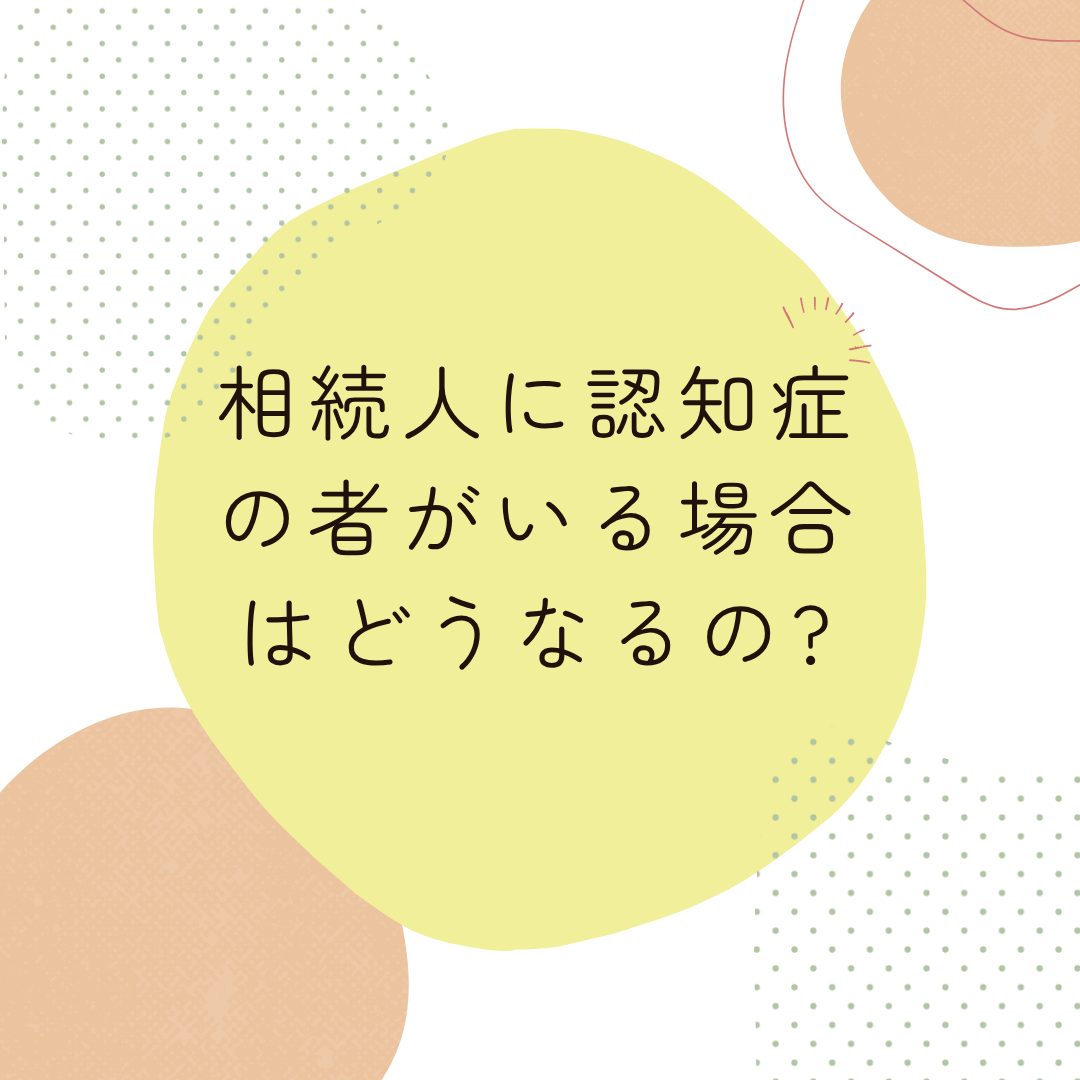
相続人の中に認知症の方がいる場合でも、その方は他の相続人と同じように法定相続分を相続します。しかし、認知症の方は、意思能力がないため、相続手続を行うことができません。特に遺産分割協議の場面では、相続人全員の合意が必要であることから、手続きが止まりかねません。以下で詳しく説明します。
>>遺産分割協議がまとまらない…次の手段「調停」「審判」とは?流れと費用を解説
意思能力とは
法律行為(例: 遺産分割協議等)を行うためには、本人に意思能力が必要です。意思能力とは、物事の判断や行為の結果を理解し、自ら選択できる能力を指します。認知症の方の認知機能低下が軽度で意思能力があると判断されるときは、場合によっては自身で遺産分割協議に参加することが可能です。
成年後見制度の利用
認知症の方が意思能力を欠く状態にある場合は、家庭裁判所に申し立てを行い、成年後見人を選任することが一般的です。
成年後見制度の概要
• 後見人の役割
成年後見人は、認知症の方に代わって法律行為を行う代理人です。遺産分割協議では、成年後見人がその認知症の方の利益を守りながら協議に参加します。
• 後見人選任の流れ
家庭裁判所に申し立てを行い、適切な後見人を選任してもらいます。後見人は昨今親族が選任されることは稀で、中立的な立場の弁護士や司法書士などの専門職が選ばれることが多いです。
まとめ
相続人に認知症の方がいる場合、その方の意思能力の有無によって対応が異なります。意思能力がない場合は、成年後見人や特別代理人の選任が必要です。これにより、認知症の方の権利や利益を守りつつ、適切な遺産分割を進めることが可能になります。少しでも意思能力が怪しい相続人がいる場合は、具体的な対応方法や手続きについて、弁護士に相談することでスムーズに進めることができるといえるでしょう。
>>「争族」を避けるために!弁護士が教える遺産分割協議の基本と揉めやすい4つのケース

広島大学(夜間主)で、昼に仕事をして学費と生活費を稼ぎつつ、大学在学中に司法書士試験に合格。相続事件では、弁護士・税理士・司法書士の各専門分野における知識に基づいて、多角的な視点から依頼者の最善となるような解決を目指すことを信念としています。
広島大学法科大学院卒業
平成21年 司法書士試験合格
令和3年4月 横須賀支部後見等対策委員会委員
令和5年2月 葉山町固定資産評価審査委員会委員
令和6年10月 三浦市情報公開審査会委員
令和6年10月 三浦市個人情報保護審査会委員
令和7年1月 神奈川県弁護士会横須賀支部役員幹事
令和7年3月 神奈川県弁護士会常議員















