相続人ではなくても寄与分を主張することはできますか。
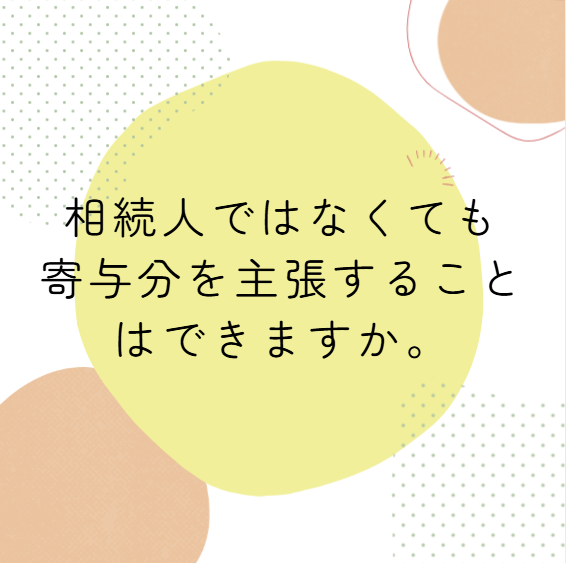
相続人ではない人が寄与分を主張することはできません。しかし、2019年の民法改正によって導入された「特別の寄与制度」を活用することで、被相続人に対して特別な貢献をした場合、その対価を請求できる可能性があります。この制度は、相続人ではない親族にも適用される点が特徴です。
>>特別受益と寄与分とは?
1. 寄与分の基本的な対象者
寄与分は、被相続人の財産の維持・増加に特別な貢献をした法定相続人に認められる制度です(民法第904条の2)。したがって、法定相続人以外の人が寄与分を主張することはできません。
2. 特別の寄与制度について
相続人ではない親族が被相続人に対して特別な貢献をした場合には、「特別の寄与制度」を活用することができます。
(1) 対象者
特別の寄与制度の対象者は、相続人ではない親族に限定されます。
たとえば、次のようなケースが該当します:
・被相続人の子の配偶者(義理の息子・娘)
・内縁の配偶者
・甥や姪
(2) 請求できる条件
特別寄与料を請求するためには、以下の条件を満たす必要があります:
被相続人の財産の維持・増加に対して、無償で特別の貢献をしたこと
例:長期間にわたる介護や家業の手伝い等
貢献が特別であること(通常の扶養義務の範囲を超える必要があります)
(3) 請求の手続き
特別寄与料は、相続人に対して金銭を請求する形で行います。遺産分割協議の中で話し合いを行うことが一般的ですが、協議がまとまらない場合は家庭裁判所に協議に代わる処分を請求することができます。
しかしながら、被相続人の死亡を知ってから6か月以内に請求しないといけないため、話し合いで折り合いがつかない場合は、早めに家庭裁判所に協議に代わる処分を請求すべきでしょう。
>>遺産の分け方で揉めている方はこちら
3. 弁護士への相談をお勧めする理由
特別の寄与制度の利用や金銭請求には、特別な貢献を立証する必要があります。具体的な証拠の収集や請求手続きは法的な知識を要するため、弁護士に相談することでスムーズな対応が可能になります。
>>円満な遺産分割を終えることを望まれる方へ
この記事の執筆者

弁護士法人TLEO 虎ノ門法律経済事務所横須賀支店
横須賀支店長・パートナー弁護士・税理士
中村 賢史郎
保有資格弁護士、税理士、司法書士有資格
専門分野相続事件・離婚事件・不動産事件・破産事件を主に取り扱う
広島大学(夜間主)で、昼に仕事をして学費と生活費を稼ぎつつ、大学在学中に司法書士試験に合格。相続事件では、弁護士・税理士・司法書士の各専門分野における知識に基づいて、多角的な視点から依頼者の最善となるような解決を目指すことを信念としています。
広島大学(夜間主)で、昼に仕事をして学費と生活費を稼ぎつつ、大学在学中に司法書士試験に合格。相続事件では、弁護士・税理士・司法書士の各専門分野における知識に基づいて、多角的な視点から依頼者の最善となるような解決を目指すことを信念としています。
経歴広島大学法学部夜間主卒業
広島大学法科大学院卒業
平成21年 司法書士試験合格
令和3年4月 横須賀支部後見等対策委員会委員
令和5年2月 葉山町固定資産評価審査委員会委員
令和6年10月 三浦市情報公開審査会委員
令和6年10月 三浦市個人情報保護審査会委員
令和7年1月 神奈川県弁護士会横須賀支部役員幹事
令和7年3月 神奈川県弁護士会常議員
広島大学法科大学院卒業
平成21年 司法書士試験合格
令和3年4月 横須賀支部後見等対策委員会委員
令和5年2月 葉山町固定資産評価審査委員会委員
令和6年10月 三浦市情報公開審査会委員
令和6年10月 三浦市個人情報保護審査会委員
令和7年1月 神奈川県弁護士会横須賀支部役員幹事
令和7年3月 神奈川県弁護士会常議員















