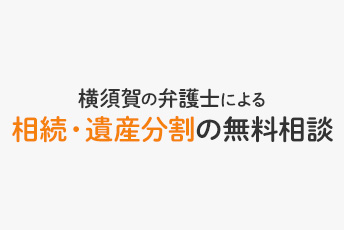遺言の内容を確実に実行して欲しい(遺言執行者選任)
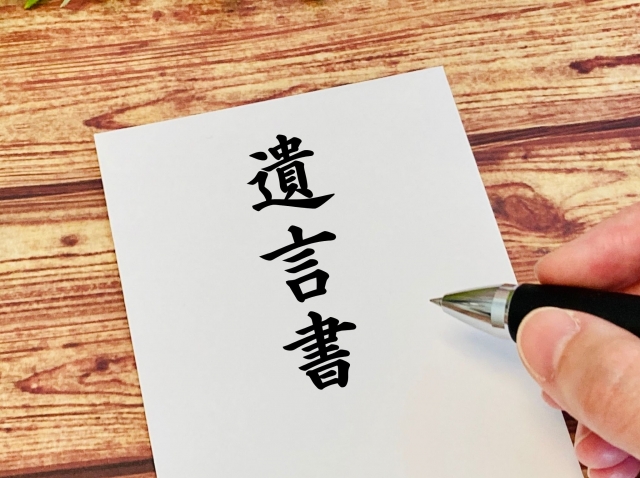
遺言書は、あなたの死後、残された家族に想いを伝え、財産を円満に引き継がせるための、非常に重要な法的文書です。しかし、遺言書は「書けば終わり」ではありません。その内容を法的な手続きに則って、一つひとつ正確に実現していく「遺言執行」というプロセスが不可欠です。
遺言執行は、時に複雑な手続きや、相続人間の感情的な対立への対応が求められます。あなたの最後の想いが、手続きの途中で滞ったり、争いの種になったりすることのないよう、専門家である弁護士に「遺言執行者」として、その実現を託しませんか。
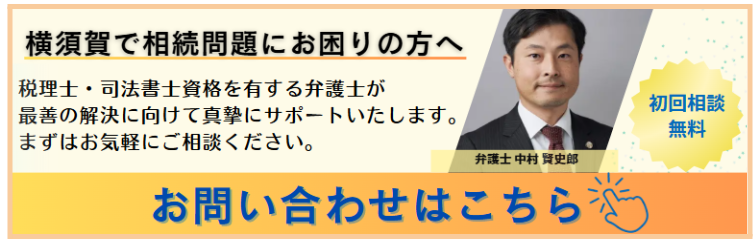
遺言執行に関する、こんなお悩み・ご不安はありませんか?
- 遺言書は作成したいが、死後、その内容が本当に実現されるか不安だ。
- 相続人同士の仲が悪いため、特定の相続人に執行を任せると、トラブルになりそうだ。
- 不動産の名義変更や預貯金の解約など、煩雑な手続きで子供たちに負担をかけたくない。
- 相続人ではない第三者への遺贈など、複雑な内容の遺言を確実に実現したい。
- 親の遺言で遺言執行者に指定されたが、具体的に何をすれば良いか分からず困っている。
ご家族を遺言執行者にする場合に潜むリスク
遺言執行者は、相続人の一人をご自身の遺言書で指定することも可能です。しかし、相続人が遺言執行者を務める場合、以下のようなリスクが伴います。
- 手続きの停滞:相続手続きに関する専門知識がないため、書類の不備などで金融機関や法務局での手続きが滞り、完了までに多大な時間がかかってしまう。
- 相続人間の対立:他の相続人から「執行のやり方が不公平だ」「財産を隠しているのではないか」と疑われ、新たな紛争の原因となる。
- 精神的な負担:他の相続人からの問い合わせや要求の窓口となり、大きな精神的負担を強いられる。
- 法的責任:遺言執行者は、善良な管理者として任務を行う義務を負います。万が一、手続きを誤って他の相続人に損害を与えた場合、損害賠償を請求されるリスクもあります。
専門家である弁護士を遺言執行者に指定する4つのメリット
これらのリスクを回避し、あなたの想いを最も確実かつ円満に実現するのが、専門家である弁護士を遺言執行者に指定する方法です。
① 中立・公平な立場で、相続人間のトラブルを防ぐ
弁護士は、特定の相続人の味方ではなく、あくまで「遺言書の内容を実現する」という故人の意思の代理人です。中立・公平な第三者として、全ての相続人に対して透明性の高い手続きを行うため、無用な疑念や対立が生じるのを防ぎます。
② 複雑な相続手続きを、迅速かつ正確に進められる
相続財産の調査から、財産目録の作成、預貯金の解約、不動産の名義変更、株式の移管まで、法律と実務に精通した専門家が、一切の手続きを迅速かつ正確に行います。
③ 他の相続人や第三者との交渉をスムーズに行える
もし、遺言の内容に納得しない相続人が現れたり、金融機関などが手続きに非協力的であったりした場合でも、弁護士が法律に基づき、説得・交渉することで、円滑に手続きを進めることができます。
④ ご家族を、煩雑な手続きと精神的負担から解放する
弁護士が全ての窓口となり、手続きの矢面に立つことで、ご家族は煩雑な作業や、親族間の対立から解放されます。これは、故人が残せる、最後の「思いやり」とも言えるでしょう。
当事務所は、皆様の複雑な相続問題を解決するために、他にはない強みを持っています。
- ①1972年創立、所属弁護士数約100名の実績と経験
1972年の創立以来、半世紀にわたり数多くの相続案件を手掛けてまいりました。約100名の弁護士が所属しており、それぞれの事案で蓄積された豊富な判例知識と実務経験を基に、最適な解決策をご提案します。 - ②税理士・司法書士有資格の弁護士が対応
相続問題、特に不動産や多額の財産が関わるケースでは、税務の視点が欠かせません。当事務所横須賀支店には、税理士・司法書士有資格の弁護士が在籍しています。法務と税務、登記の全方面から多角的なアドバイスをして最善の解決を目指します。 - ③グループ内で連携したワンストップサービス
当事務所は、司法書士、税理士、土地家屋調査士、不動産鑑定士、不動産仲介業者がグループ内に存在するため、各専門家と緊密に連携し、あらゆる手続きをワンストップでサポートすることが可能です。
相続にお困りの方は虎ノ門法律経済事務所にご相談ください。
遺言執行者の指定は、あなたの遺言書が、単なる紙切れで終わるか、それとも実現されるかを左右する、極めて重要な項目です。残されるご家族が円満にあなたの意思を受け継ぎ、新たな一歩を踏み出せるよう、その最後の重要な任務は、ぜひ私たち専門家にお任せください。
>>無料相談の流れはこちら本記事は、令和7年8月14日時点の法令等に基づき作成しております。法改正などにより、最新の情報と異なる場合がございます。具体的な事案については必ず弁護士にご相談ください。

広島大学(夜間主)で、昼に仕事をして学費と生活費を稼ぎつつ、大学在学中に司法書士試験に合格。相続事件では、弁護士・税理士・司法書士の各専門分野における知識に基づいて、多角的な視点から依頼者の最善となるような解決を目指すことを信念としています。
広島大学法科大学院卒業
平成21年 司法書士試験合格
令和3年4月 横須賀支部後見等対策委員会委員
令和5年2月 葉山町固定資産評価審査委員会委員
令和6年10月 三浦市情報公開審査会委員
令和6年10月 三浦市個人情報保護審査会委員
令和7年1月 神奈川県弁護士会横須賀支部役員幹事
令和7年3月 神奈川県弁護士会常議員