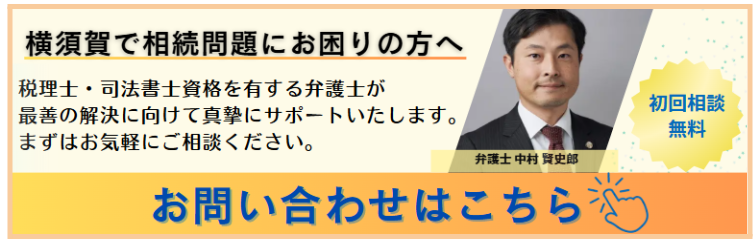遺言書はなぜ必要?3つの種類と書き方
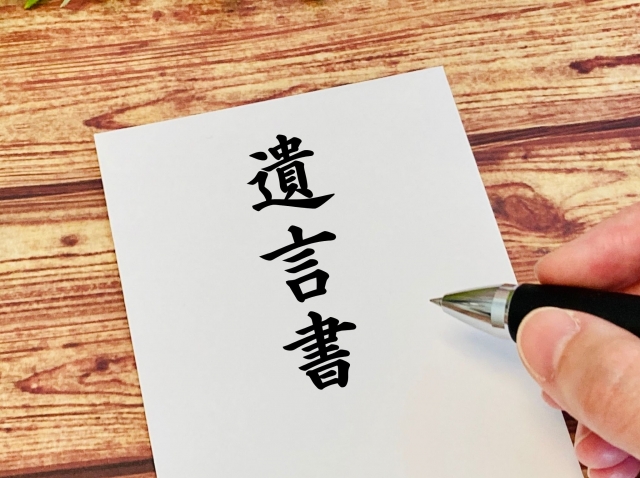
「自分の死後、残された家族が相続で揉めてしまったら…」 「お世話になったあの人に、確実に財産を渡したい」 「相続手続きで、子どもたちに面倒をかけたくない」
上記のようなトラブルについて当事務所も横須賀・逗子・葉山・三浦エリアの方からよくご相談を受けます。ご自身の意思を明確にし、大切なご家族を守るために最も有効な手段が「遺言書」の作成です。
この記事では、相続問題に長年携わってきた税理士・司法書士有資格の弁護士が、遺言書の必要性から具体的な書き方、そして思わぬ落とし穴まで、網羅的に解説します。ご自身の状況に最適な遺言書作成のヒントがきっと見つかるはずです。
そもそも遺言書とは?なぜ作成すべきなのか
遺言書とは、ご自身の財産を「誰に」「何を」「どれだけ」渡すのかを記した、法的な効力を持つ最後の意思表示をする文書です。遺言書がない場合、民法で定められた「法定相続人」が「法定相続分」に従って遺産を分けることになります。
一見公平に見えるこの方法ですが、実際には様々なトラブルの火種となるケースが少なくありません。遺言書を作成しなかったために起こりうる、3つの代表的な問題を見ていきましょう。
希望通りの遺産分割ができない
法定相続のルールは画一的です。「事業の承継に貢献してくれた長男に会社株式を集中させたい」「長年介護をしてくれた長女に多めに財産を残したい」といった、ご自身の特別な想いや家族それぞれの事情を反映させることはできません。
また、内縁の妻や事実婚のパートナー、お世話になったご友人など、法定相続人以外の方には、遺言書がなければ一切財産を渡すことができません。ご自身の希望通りの財産承継を実現するためには、遺言書の作成が不可欠です。
相続手続きが複雑化・長期化する
遺言書がない場合、相続人全員で「遺産分割協議」を行い、全員の合意を得て「遺産分割協議書」を作成する必要があります。
この手続きのためには、まず「誰が相続人なのか」を確定させるために、被相続人(亡くなった方)の出生から死亡までの全ての戸籍謄本等を取り寄せなければなりません。疎遠な親族や、会ったこともない相続人がいる場合、その調査だけで数ヶ月を要することもあります。
さらに、銀行口座の解約や不動産の名義変更といった手続きのたびに、相続人全員の署名と実印、印鑑証明書が必要となり、残されたご家族に大きな負担を強いることになります。
公正証書遺言や、法務局に保管された自筆証書遺言があれば、こうした手続きが大幅に簡素化され、相続人の負担を大きく減らすことができます。
遺産分割協議がまとまらない
相続は、時に「争続」と揶揄されるほど、親族間のトラブルに発展しやすい問題です。遺産分割協議では、各相続人の利害が対立し、感情的なしこりも相まって、話し合いが全く進まないケースが後を絶ちません。
- 「長男は生前に住宅資金の援助を受けているはずだ」
- 「実家(不動産)の価値でもめている」
- 「親の預金がいつの間にか減っている」
こうした問題が噴出し、一度関係がこじれると、解決までに何年もかかることも珍しくありません。最悪の場合、家庭裁判所での調停や審判に移行し、親族間の断絶に繋がることもあります。
遺言書は、こうした無用な争いを防ぎ、円満な相続を実現するための「道しるべ」となるのです。
遺言書には3つの種類がある!それぞれの特徴と書き方
遺言書には、主に「自筆証書遺言」「公正証書遺言」「秘密証書遺言」の3種類があります。それぞれにメリット・デメリットがあるため、ご自身の状況に合わせて最適な方式を選ぶことが重要です。
1. 自筆証書遺言
ご自身で手書きで作成する最も手軽な遺言書です。
メリット
- いつでも手軽に作成できる
- 費用がかからない
- 内容を誰にも知られずに済む
デメリット
- 法律で定められた形式を欠くと無効になるリスクがある
- 紛失、改ざん、隠匿のリスクがある
- 発見後、家庭裁判所での「検認」手続きが必要
【書き方のポイント】
- 全文、日付、氏名を自書(手書き)する:後述する財産目録以外はパソコンや代筆は認められません。
- 押印する:認印でも可能ですが、実印が望ましいです。
- 財産目録はパソコン作成も可能:ただし、財産目録の全ページに署名・押印が必要です。
※法務局での保管制度
2020年から、作成した自筆証書遺言を法務局で保管してもらえる制度が始まりました。これにより、紛失や改ざんのリスクがなくなり、面倒な「検認」手続きも不要になります。ただし、法務局は内容の有効性までは審査してくれないため、法的に不備のない遺言書を作成することが大前提です。
2. 公正証書遺言
公証役場で、公証人と証人2名の立会いのもとで作成する、最も確実で安全な遺言書です。
メリット
- 形式不備で無効になる心配がほぼない
- 原本が公証役場に保管されるため、紛失・改ざんのリスクがない
- 家庭裁判所での「検認」が不要
- 相続手続きがスムーズに進む
デメリット
- 作成に費用と手間がかかる
- 証人が2名必要になる
- 内容を公証人と証人に知られる
【作成のポイント】
公証役場との事前の打ち合わせが必要になります。どのような内容の遺言にしたいか、財産内容はどのようなものか、必要書類は何かなどを確認しながら進めます。当事務所のような専門家にご依頼いただければ、文案作成から公証役場との調整、証人の手配まで一括してサポートいたします。
3. 秘密証書遺言
遺言の内容を誰にも知られずに、その存在だけを公証役場で証明してもらう方式です。
メリット
- 内容を秘密にできる
- 偽造・変造のリスクを防げる
デメリット
- 内容に不備があると無効になるリスクがある(自筆証書遺言と同様)
- 家庭裁判所での「検認」が必要
- 作成に費用と手間がかかる
- 利用されるケースは非常に少ない
【作成のポイント】
自筆証書遺言の「手軽さ」と公正証書遺言の「安全性」のメリットが薄く、手続きが煩雑なため、実務上はあまり利用されていません。特別な事情がない限りは、自筆証書遺言(法務局保管制度利用)または公正証書遺言のどちらかを選択することをお勧めします。
遺言書を作成する上での重要な注意点
ご自身の希望を完璧に反映したと思える遺言書でも、ある重要な点を見落とすと、かえって紛争の火種になることがあります。それは「遺留分」への配慮です。
遺留分とは、兄弟姉妹以外の法定相続人(配偶者、子、親など)に法律上保障された、最低限の遺産の取り分のことです。「愛人に全財産を譲る」といった遺言書を作成しても、相続人は遺留分を侵害されたとして、財産を受け取った人に対して金銭の支払いを請求(遺留分侵害額請求)できます。
良かれと思って書いた遺言書が原因で、残された家族が裁判で争うことになっては本末転倒です。遺留分を考慮した財産の配分や、なぜそのような分け方にしたのかを「付言事項」として書き添えるなど、争いを未然に防ぐ工夫が重要になります。
>>遺産をもらえない内容の遺言書が見つかった方へ(遺留分について)
専門家への相談が安心な理由
「遺言書くらい自分で書けるだろう」とお考えになる方もいらっしゃるかもしれません。しかし、法的に有効で、かつ、将来の紛争を未然に防ぐ「本当に意味のある遺言書」を作成するには、専門的な知識と経験が不可欠です。
相続の専門家である弁護士にご相談いただくことで、以下のようなメリットがあります。
- 法的に無効になるリスクをなくせる
- 「遺留分」など将来の紛争リスクを考慮した内容にできる
- 相続税のシミュレーションを行い、節税を意識した分割案を提案できる
- 不動産の名義変更(相続登記)や相続税申告まで見据えた準備ができる
- ご自身の本当の想いを法的な文章に落とし込める
私たち虎ノ門法律経済事務所は、皆様に安心して未来を託していただけるよう、盤石の体制を整えています。
①1972年創立、所属弁護士数約100名の実績と経験
当事務所は、半世紀以上にわたる歴史の中で、数多くの相続案件を解決に導いてまいりました。豊富な経験を持つ弁護士が、あらゆるケースに的確に対応し、お客様にとって最善の遺言書作成をサポートします。
②税理士・司法書士有資格の弁護士が対応
当事務所には、弁護士資格に加えて、税理士や司法書士の資格も併せ持つ弁護士が在籍しています。そのため、法的な問題だけでなく、税務や登記まで含めた、より高度で多角的な視点から、お客様の財産状況やご希望に最適な遺言書プランをご提案できます。
相続は、遺言書作成から財産調査、遺産分割協議、そして万一のトラブル対応まで、非常に幅広く、専門的な対応が求められます。
- 遺産の内容を網羅的に調査してほしい
- 借金も相続してしまうのか不安だ
- 遺産の管理方法がわからない
- 他の相続人の代理人弁護士から手紙が届いた
このようなお悩みにも、当事務所は迅速かつ的確に対応いたします。
相続にお困りの方は虎ノ門法律経済事務所にご相談ください
遺言書は、ご自身の人生の集大成であり、残される大切なご家族への最後の贈り物です。その想いを確実に、そして円満な形で未来へ繋ぐために、ぜひ一度、私たち専門家の声をお聞かせください。
虎ノ門法律経済事務所では、相続に関する初回のご相談は無料でお受けしております。まずはお気軽にお問い合わせいただき、皆様のお悩みやご希望をお聞かせいただければ幸いです。

広島大学(夜間主)で、昼に仕事をして学費と生活費を稼ぎつつ、大学在学中に司法書士試験に合格。相続事件では、弁護士・税理士・司法書士の各専門分野における知識に基づいて、多角的な視点から依頼者の最善となるような解決を目指すことを信念としています。
広島大学法科大学院卒業
平成21年 司法書士試験合格
令和3年4月 横須賀支部後見等対策委員会委員
令和5年2月 葉山町固定資産評価審査委員会委員
令和6年10月 三浦市情報公開審査会委員
令和6年10月 三浦市個人情報保護審査会委員
令和7年1月 神奈川県弁護士会横須賀支部役員幹事
令和7年3月 神奈川県弁護士会常議員